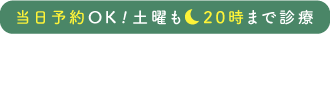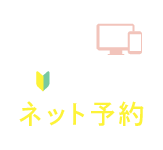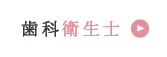喫煙は肺がんや高血圧など身体にさまざまな悪影響を及ぼします。
たばこの健康への害は多くの方が認識しているのではないでしょうか。
歯周病はお口の生活習慣病といわれていますが、喫煙の習慣が歯周病と深く関係していると言われています。
そこで今回は喫煙がお口にもたらす影響について詳しくご紹介します。
【たばこの3大有害物質】
たばこの中には「ニコチン」「タール」「一酸化炭素」の3大有害物質が含まれています。
この中で「ニコチン」は依存度が高く、たばこをやめたいので中々やめられないという話を聞いた方のいるのではないでしょうか。
そのため、禁煙しようと思っても難しい場合が多くなります。
また、「タール」はべとべとしていて発がん性の物質で、家の壁が黄ばんだようになってベタベタするのは、タールが原因です。
また、「一酸化炭素」があると、酸素と結びつくはずのヘモグロビンが一酸化炭素と結びついてしまい、酸素の供給が妨げられてしまいます。
【たばこがお口に与える影響】
たばこを継続して吸っていると、歯ぐきが黒ずんでしまいます。
これは、一酸化炭素とニコチンが原因です。
ニコチンは血流が悪くなり、一酸化炭素が酸素ではなくヘモグロビンと結びつくことで血液の色が黒ずんでしまいます。
また、歯ぐきの黒ずみだけでなく厚みも増してしまいます。
そのほかには、たばこを吸っていると独特の口臭がしたり、味覚が鈍感になったりします。
禁煙をすると、味覚が戻って食事が美味しく感じられるのはこのためです。
そして、喫煙している方は非喫煙の方に比べて喉頭がんや咽頭がんが約3倍に増えるデータが出ています。
【たばこと歯周病の関係】
喫煙の習慣があると血流が悪くなり、歯ぐきに栄養が行き渡りにくくなります。
そうすると、歯周病菌と戦う「白血球」が減ってしまい、歯周病が悪化します。
この悪循環で歯周病が増えて進行してしまいます。
また、一般的には歯周病になって炎症が起きると歯ぐきが出血しやすくなり、その症状で歯ぐきに異常が起きていることが分かります。
しかし、たばこを吸っていると血管の収縮作用で出血が抑えられているので、歯周病になっていることに気づきにくくなります。
歯周病は喫煙をしていなくて、自覚症状が少なく、いつの間にか進行していることも少なくありません。
さらに喫煙していると自覚症状が抑えられて、初期~中期の段階でも気づかない方が多くなってしまうのです。
さらに、喫煙している方が歯周病になった際に起きることは「治りにくい」ことです。
酸素や栄養が不足して免疫力が低下しているので、治癒しにくい環境になります。
せっかく歯周病の外科治療をしても、喫煙している方は治りにくいのです。
また、ヤニでベトベトしているので汚れがつきやすく、落としにくいので、歯周病の原因になりやすい環境になります。
【副流煙にも注意が必要】
喫煙の怖いところは副流煙で周りの方にも影響を及ぼしてしまうことです。
歯周病でも、受動喫煙の場合でも悪影響があることが分かっており、ご自分だけの問題ではありません。
【まとめ】
喫煙は身体にさまざまな影響を及ぼします。
それはお口の中にも関係があり、免疫力を低下させて、細菌を活発にしてしまいます。
特に歯周病は気づきにくく、悪化しやすく、治りにくいと言われています。
喫煙は依存してしまうこともあると思いますが、多くの健康被害につながります。
お口の環境を整える上では喫煙をおすすめします。
禁煙外来など禁煙をサポートしてくれる場所もありますので、ご自身の健康のために喫煙を考えてみてくださいね。